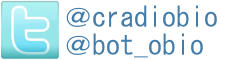【イベントのお知らせ】
DREAM SHIP Science Talk Live
教科書が教えないホットな科学の講演会26
「さよならベテルギウス」
2012年2月11日(土)10時30分〜11時30分
DREAM SHIP 下関市生涯学習プラザ 1階音楽練習室(山口県下関市)
入場無料・事前申し込み不要
Talk & Music Diner Voynich in Tokyo 2012
「ここまで進んだ次世代医薬品」
2012年3月17日(土)19時〜
Loft A (東京・阿佐ヶ谷)
前売りチケット発売中 >> ローソンチケット
【ヴォイニッチの科学書《有料版》番組要旨】
2011年12月31日
Chapter-373 太陽観測衛星「ひので」が発見した太陽の新事実
(前回の放送|トップページ|次回の放送)
▼太陽観測衛星「ひので」が太陽風の始まりを発見
衛星「ひので」に搭載されているX線望遠鏡(XRT7)を使って黒点近くのコロナを観測したところ、秒速140kmでコロナプラズマが流れ出しているらしい現象を観測することに成功しました。黒点近傍から流れ出す太陽風は最終的に秒速400km程度にまで加速されるので、「ひので」がとらえた秒速140kmの流れは太陽風の誕生の様子を世界で初めてとらえたものと考えられています。
▼太陽観測衛星「ひので」が黒点の微細構造を観測
黒点は太陽に付随する構造の中でも最も古くから観測されているものの一つですが、その内部構造は謎でした。「ひので」に搭載された太陽表面の構造を観測する可視光・磁場望遠鏡(SOT)のデータによると黒点は放射状の明暗の筋構造からなる「半暗部」と中央の「暗部」を持ち、暗部の中には暗部輝点と呼ばれる小さな明るい構造があるようです。
また、エバーシェッド流と呼ばれる暗部から黒点の外周へ向かう太陽面に沿ったほぼ水平なプラズマの流れがあります。エバーシェッド流は複数の流れが縞々に並んだ構造をしていますが、黒点の中心に近い暗部側には高温プラズマの湧き出しが、明るい外周側には音速を超える下降流が存在することが確認され、黒点の中心と黒点周辺の明るい領域で対流現象が起きていることが明らかになりました。
▼「ひので」が観測した太陽の北極と南極
地球は太陽の赤道上空を公転していますので、太陽の北極や南極は、地球を周回する観測衛星では観測を行いにくい地域です。この領域を2006年に打ち上げられた日本の太陽観測衛星「ひので」が観測しています。南北極域は太陽の活動がもっとも弱まる時期にはN極またはS極に磁場の特性が均一になり、X線で観測すると暗い穴のように見える「コロナホール」が広がり高速太陽風がそこから吹き出しています。
「ひので」の可視光・磁場望遠鏡による観測によって極域において磁場は1キロガウス以上の強度を持つ多数の磁束管として存在し、水平磁場も極表面を覆い尽くしていることがわかりました。さらに、同じ場所をエックス線で観測すると、これまで比較的静かだと思われていた極地域が、秒速1000kmにも達するエネルギー放出の高速な流れであるジェットが多数存在する落ち着きのない領域であることが分かりました。
また極域は内部に大規模な対流構造が確認されましたが、その起源と意味するところはまだよくわかっていません。
また、太陽の表面からは外へ向かって炎の柱が吹き出していてこれをプロミネンスと呼びますが、「ひので」の観測によってプロミネンスの中に無数の泡が存在していることが分かりました。この泡はまるで水の中の泡のように上方へ浮かんでいくことも確認されました。プロミネンスが水のような流体ではなく、重く冷たいプラズマが重力による大洋側へ引っ張る力と、磁場による外向きの力のバランスで支えられた磁気平衡構造で、理屈で言えば、このような泡のような現象は起きるはずがないのですが、実は、磁場構造は泡のようなプルームを作り、まるで沸き立っているかのようであることが分かり、太陽の謎がまた新たに増えることになりました。
◇ ◇ ◇
(FeBe! 配信の「ヴォイニッチの科学書」有料版で音声配信並びに、より詳しい配付資料を提供しています。なお、配信開始から一ヶ月を経過しますとバックナンバー扱いとなりますのでご注意下さい。)
Science-Podcast.jp
制作

![]()
![]()
科学コミュニケーター 中西貴之(メール / 活動履歴)
アシスタント BJ
|
ご案内
|
||
| ■ | ヴォイニッチの科学書ポッドキャストは有料コンテンツです | |
| ▼ダウンロードしていただくためにはオーディオブック配信国内最大手オトバンク社の「FeBe!」でお手続きをお願いいたします。月額525円です。 ▼このページの閲覧は無料です。 ▼インターネットラジオ局くりらじより配信中の「ちょきりこきりヴォイニッチ」は無料です。 |
||
|
研究支援活動
|
||
| ■ | ヴォイニッチの科学書有料版の売り上げの一部を日本の研究支援のために研究機関に寄付させていただいています。 | |
|
お知らせ
|
||
| ■ ■ |
twitter ■twilog ■Facebook PS Home クラブ ヴォイニッチの科学書の使い方 |
|
|
最新科学をポストする twitter bot
ぼっとびお
|
||
| ■ | twitter ■twilog | |
|
無料配布試聴版
下記の回は有料版と同じ内容を無料でお楽しみいただけます |
||
| ■ | Chapter-321 太陽系に関する近頃の発見 | |
| Chapter-321 番組MP3 Chapter-321 配付資料pdf | ||
| ■ | Chapter-315 グリーゼの惑星 | |
| 番組全編 MP3 配付資料 pdf | ||
| ■ | サイエンスアゴラ2010特番 | |
| pdf 前半 pdf 後半 | ||
| ■ | Chapter-253 水にも構造がある | |
| 配付資料 pdf | ||
|
|
このページはインターネット放送局くりらじが毎週放送している科学情報ネットラジオ番組「ヴォイニッチの科学書」の公式サイトです。放送内容の要旨や補足事項、訂正事項などを掲載しています。
「ヴォイニッチの科学書」では毎週最新の科学情報をわかりやすく解説しています。番組コンセプトはこちらをご覧ください。>>クリック
[この番組の担当は・・・]
ナビゲーター 中西貴之 obio@c-radio.net
1965年生まれ
島生まれの島育ち
応用微生物学専攻
現在化学メーカーの研究所勤務
所属学会 日本質量分析学会 他
日本科学技術ジャーナリスト会議会員
ナビゲーター BJ
インターネット放送局くりらじ局長